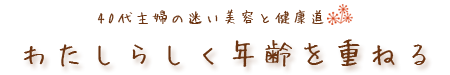Kindleで 与謝野晶子さん訳の『源氏物語』 を再読中(@100円)。
改めて読んでいると、帚木(ははきぎ)の章にある「雨夜の品定め」を相当に面白く眺めました。
独身時代はサラリと流していたシーンですが、既婚の身となっている現在読むと何やら考えさせられます。
『源氏物語』帚木(ははきぎ)の章、雨夜の品定めとは。
源氏物語の帚木(ははきぎ)の巻で、五月雨の一夜、光源氏や頭中将(とうのちゅうじょう)たちが女性の品評をする場面。雨夜の物語。また一般に、人物を品評すること。
コトバンクより
世界最古の長編小説と言われる『源氏物語』を知らない人はいないと思いますが、簡単に話の内容を説明しますと帝の皇子として生まれた光源氏の栄華と苦悩の生涯を描いた小説。
光源氏はプレイボーイとしても有名ですね。
「雨夜の品定め」とは、そんな光源氏がプレイボーイの片鱗を見せるきっかけになった日かも(?)。そう、若き日(17歳の頃)、遊び人のお兄さんがたに色々と女の薫陶(?)を受けたシーンをが「雨夜の品定め」。
ま、言ってみれば当時のイケメン(いずれもボンボンで超高級エリート官僚)たちが・・・
「あの女、なかなかいいぜ」「オレはこんな女が好きだ☆」「賢いだけの女は疲れるぜ」「出来る女房ってのも・・・」「オレが他の女に目移りをしてもあの女は健気に待っていたぜー」「マジかよ、羨ましいー」
と女でのしくじりやら自慢やらを赤裸々に語った結果、「男の欲望を体現した理想の女とはいかなる女なのか!?」と語るシーン。
それにしても、これを千年の昔に女人が描いたということが凄いなぁと妙に感心します。
↓この本、読みたい!読みたい!買ってやるぜ!譲ってやるぜ!という方、絶賛募集中。清少納言verもあるようなので、そちらも募集中♡コメント欄で応募を待つ。
かくして、平安の世の男たちが思い描く理想の女とは。
「雨夜の品定め」登場人物。
- 光源氏(時の帝桐壺帝の第二皇子。イケメンオブイケメン)
- 頭中将(左大臣の息子。光源氏の義兄。イケメン)
- 左馬頭(そこそこ中流)
- 藤式部丞(そこそこ中流)
※ちなみに皆さん、そこそこ名うての風流人(つまり、遊び人)。
結論。
中の品の女に面白い女がいるらしい。
つまり、現代風に解釈すると。
そう、結論として理想の女は「中の品(中流)の女」。
この「中の品の女」とは、現代でいうと羽振りのいい中小企業の社長令嬢あたりを指していると思われ。庶民はお呼びじゃないのよーみたいな。
ま、これを現代語に変換すると・・・
だって、オレ様が理想とする完璧な女なんかどこにもいないんだから。
そう、女にほどほどの身分とほどほどの容貌とほどほどの性格であればOK!!!
という感じでしょうか。一瞬、ムカッとくるけれど、至極まっとうな結論だよね、と。そうだよね、それは女から見る男にも当てはまるけれど、と思ったりも。なんだか妙に安堵します。
1000年も昔から相手に求めることはさほど変わりがないんだなーと。
すみません、なんの捻りもなくて。ただ、改めて、この雨夜の品定めを読んでいると、胸に突き刺さる言葉が・・・
妻に必要な資格は家庭を預かることですから、文学趣味とか おもしろい再起などはなくてもいいようなものですが、まじめ一方で、なりふりもかまわないで、額髪をうるさがって耳の後ろへはさんでばかりいる、ただ物質的な世話だけを一生懸命にやいてくれる、そんなのではね。(一部省略)何なんですかとつっけんどんに言って自分の顔を見る最近などはたまらないではありませんか。
いろいろと「あたたた・・・」ですな。
我が身を振り返っていろいろと反省をします。すみません、物質的な世話ばかりにならないように鋭意努力をしたいな、と。
で、素直な(?)光源氏は。
この薫陶をうけた光源氏の君は中の品の女を探し、空蝉と夕顔という女人と巡りあいます。
気ぐらい高き空蝉は己がプライドのために光源氏を鮮やかにかわし、これぞ!男の理想!という夕顔は世にも恐ろしき女の嫉妬という物の怪に命をみまかることに・・・
そして、いずれの女人も光源氏に忘れがたき記憶をもたらします。が、超エリート階級の高級官僚であった彼にとってそれらは結果として、いずれもそれぞれの形で叶わぬ恋となり。
色々と考えさせられる恋の顛末。
電子書籍で読む『源氏物語』。
さて、話はそれますが、54帖もある『源氏物語』ほど電子書籍にピッタリの本はないですねー。
『源氏物語』を本で購入するとどうしても何冊も購入する必要があり、かつ、かさばることが宿命ですが、電子書籍なら端末さえあればそれでOK!というのが大きいです。
つくづくいい時代になったものだ、とシミジミしました。
久しぶりに『源氏物語』を読み返すと胸がキュンキュンします。若い頃のキュンキュンとは違う趣ですね。
それにしても、平安のこの頃は男女ともに恋愛至上主義だったのねーと妙な感慨を。たとえ夫であっても妻の恋という感情にはひれ伏したもうた、とな。